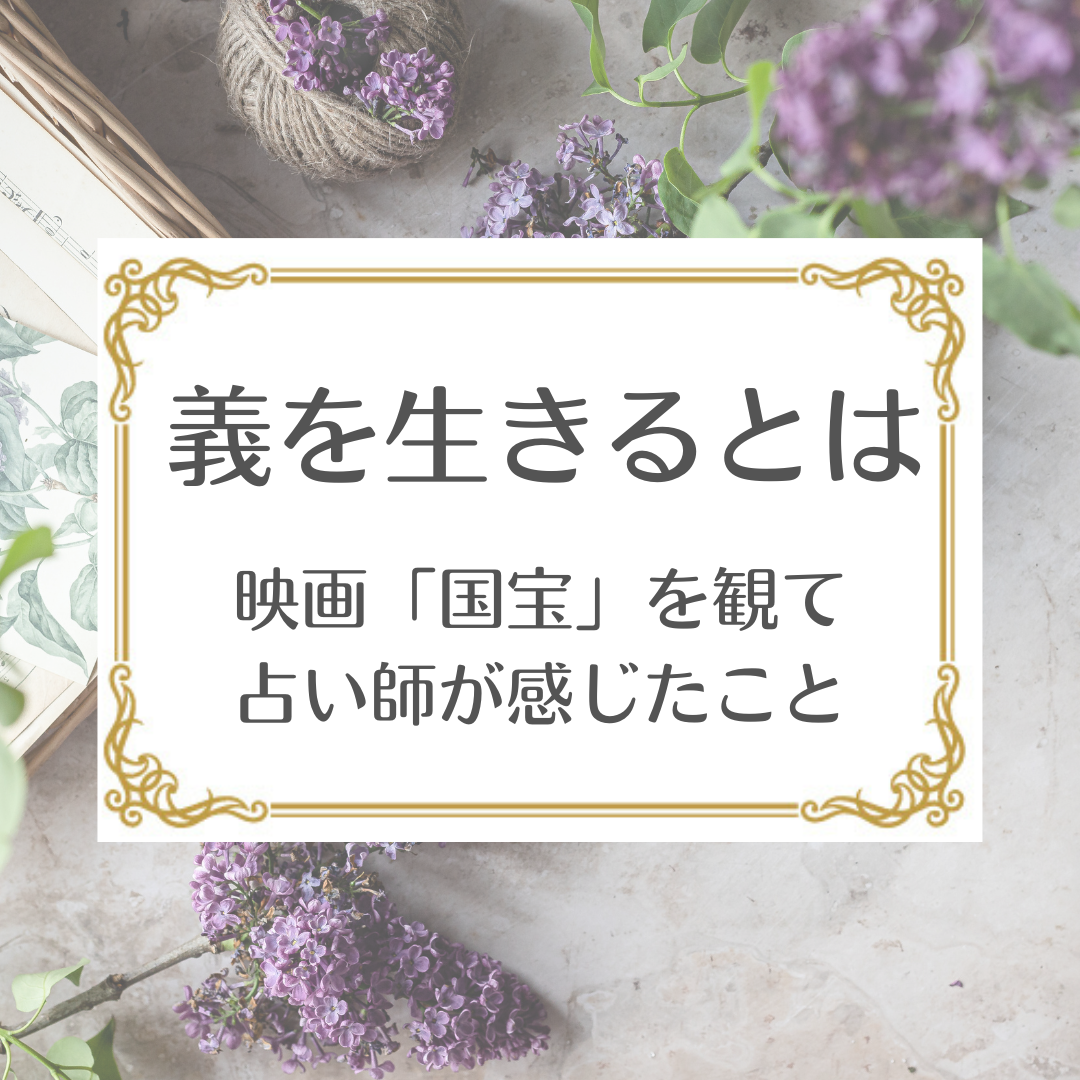大ヒット上映中の「国宝」、見てきました。
行きたいなーってずっと思ってはいたが、3時間という長時間上映との話で悩んで見れていなかったんですが
実際見に行ってみると3時間なんてあっという間で、今まで見に行くか迷っていたのがもったいなかったとすら思いました。
ぜひ行くか悩んでてまだ見れてない方は見に行ってほしいです。
ちなみに私は見終わった後、スクリーンを出てすぐそこにあった椅子に座り込んだくらい気持ちがぐっちゃぐちゃになりました(笑)

映画から気付いた「時柱」の意味
私は四柱推命という占術を使った占い師なので、占い師の観点から思ったことを書いてみようと思います。
先日Xの方でも書いたんですが
時柱には晩年こんな風に過ごしてるよっていう傾向が出ているんですが、
映画を観ながら「お客さまが手にしたい最高の未来を描くためのヒントって、この時柱にすごく詰まっているな」と強く感じました。
だからこそ占い師は、単に良いことだけを伝えるのではなく、時に耳が痛いことも誠実に伝える必要があります。
お客さまの人生の背中を押すために。
胸に響いたセリフ
映画の中でこんなセリフがあります。
「お初として生きてへんから、お初として死ねへんねん!」
主人公の吉沢亮さん演じる東一郎(喜久雄)が、曾根崎心中のお初の代役を任せられた時に、
師である二代目 花井半次郎から言われた言葉ですが、
自分に言われてるような気持ちになり、すごく胸に響きました。
私は、特に希死念慮はないし、なんなら死ぬのは怖いから死にたくないって思っていますが、すごく「死」に関心があります。
私の死生観とでも言うんでしょうか、常々こんなことを思っています。
「人は死んだときにその人の人生という物語・芸術ができあがる。その芸術はとても美しいものだ。」
でも恐らく、その美しさは人生をしっかり「自分として生きた」からこそのものなんではないだろうか。
死の場面に見た「美しさ」
この映画では重要人物が何人も亡くなります。歌舞伎が題材になっている映画でこんなに人が死ぬことをダイレクトに感じさせるなんて
予想もしていなかったのですごく衝撃でした。その中でも私が一番印象的だった人物の死についてお話します。
映画冒頭で喜久雄の父が殺されてしまうんですが、私はこの父の死ぬシーンに美を感じた。(と言うとサイコパスっぽいね)
喜久雄の父はヤクザの立花組の親分。新年会の最中に敵対する組がカチコミに来るという場面での話です。
親分なんで死んでしまうと組の存続にもかかわるし逃げるのかなと思ったんですが、父は逃げなかった。
喜久雄の父は死を覚悟して立ち向かっていったのか、勝てる戦だと思って立ち向かっていったのかは分かりかねるが
喜久雄が別室から自分を見ていることに気付いて、「よう見とけ。」と刀で敵を殺そうとするところで
別の敵対組員に銃で撃たれて死んでしまうんですよね。
喜久雄の父は恐らく死ぬかもしれないという状況でも逃げずに立ち向かったのは、これが俺の生き様だと
死ぬ最期まで「自分」で在り続けた。喜久雄父の大義を貫いたシーン。
私が喜久雄父の死ぬ場面で、美しいと感じたのはこれが理由なんだと感じる。
そして、義理兄弟のように共に歌舞伎の道を歩んできた横浜流星さん演じる花井半弥(俊坊)。
彼は生まれが歌舞伎の家で御曹司として育ってきて、当然ながら自分が跡を継ぐものだと思ってきたと思います。
ところが父である半次郎が曾根崎心中のお初の代理を東一郎に任命し、お初を演じる東一郎の姿を見て逃げ出してしまうんですよね。
ここまでの俊坊は「自分」を生きてなかったように感じます。
そして月日が経ち、半次郎が亡くなったことをきっかけに生家に戻ってきたんですが、糖尿病になってしまい足を切断することに。
足を切断したらもう舞台には立たなくなるだろうなって思ったんですが、彼は諦めなかった。
義足をつけて昔自分が抜擢されることのなかった曾根崎心中のお初を演じることにするんですよ。
この半弥が演じるお初。切なさの中にある強さがめちゃくちゃ美しかったです。
はっきりと言われてなかったと思うんですが、恐らく片方の切断していない足もお初を演じる舞台ではもうほとんど壊死に近い状態のような
表現に感じました。めちゃくちゃ辛そうに倒れながら必死に立ち上がって最後までやり遂げようとする姿だったんです。
そして残念なことにこの後、彼も亡くなってしまうんですが、彼も喜久雄父と同じように自分の大義を貫き亡くなったなと思いました。
この映画を漢字で表すなら
私はこの映画は「義」、この漢字で表せるなと思いました。
義理、不義理、大義、恩義、仁義、義足、犠牲
様々な「義」が登場人物を通して描かれていました。
東一郎の背中に入った彫り物がミミズクで、「ミミズクは捧げものを取ってくる、受けた恩を忘れない」という意味で
彫っていたんですが、劇中最後に東一郎が国宝に選ばれたのは、これまで自分に恩を与えてくれた人たちの生き様を
自分の血(=芸)として受け入れ、また芸で恩を返したんではないだろうか。
あと、「義」と言うと、四柱推命鑑定士は「五常」を思い浮かべるんではないでしょうか。
五常の義は、「人としての正しい道、道理にかなったこと」
この、人としての正しいだとか、道理にかなうって一見善行のみを指すように思いませんか?
私は自分も含め人は常に正しくない、心の中に大小それぞれ悪魔と言える存在があるものだと思っています。
劇中でも東一郎が神社で手を合わせながら悪魔と取引したんやって自分の子供に言うんですよね。
このシーンは隠し子と言え我が子に、「何も要らんから歌舞伎上手くなりたいって悪魔と取引した」って話をしてて
ほんまに悪魔やなって思った(笑)
つまり、何が言いたいかと言うと無理のある解釈かもしれませんが、
自分の大義を貫くならば自分の中にある悪魔にも目を背けずに生きることこそ正しい道ではないだろうか。
私はそのように思うんです。
東一郎にとっては身寄りもない中で自分の歌舞伎の才能を認めてもらえ引き取ってくれた半次郎、そしてその世界の中で
自分に色んなものを与えてくれた人たちへ恩を返すことが道理にかなった生き方だったように感じました。
占い師としての学び
彼ら以外にも重要な登場人物が亡くなっているんですが、みな最期の瞬間まで「自分」で在り続けた人達にように思います。
そんな彼らの生き様に映画を通して触れ、私はちゃんと「自分」を生きているだろうかと自らを省み、
そして1人の占い師としてお客様に「自分を生きる」ことをしっかりお伝えする重要性を感じたんです。
そして、そのためには、必要以上の上げ鑑定をしないこと。
折角自分のところに占いに来てくれたし嫌な思いさせたくないからってポジティブなことしか言わなかったりする占い師さんって
たまにお見かけするんですよね。私も自分が意識しないと鋭い言葉使っちゃうから優しくしないとを意識しすぎて
本質が伝えれてない時もありました。これ、お客さまを傷付けたくないんじゃなくて自分が傷付きたくないって気持ちが強い場合もあるよね。
折角来てくれたからこそお客さまが自分の人生を力強く歩んでいくためのきっかけにしてもらいたいのにこれでは意味ない。
だから、占い師もちゃんと嫌われる勇気を持たないといけないって感じます。
そうしてお客さまが自分の人生を歩むきっかけになるなら、占いは本当に意味を持つのだと思います。
さいごに
長々と分かりにくい感想を書いてしまいましたが、読んでくださった方ありがとうございました。
よく人生を変えたい、開運させていくのは「感謝すること」だよなんて色んなところで見ます。
それについては私も概ね同意なんですが、ただただ何があっても感謝すればいいと思っている人もいるように感じます。
人間は知性があり、感情のある生き物です。
情念を見て見ぬふりして生きる人生に美学はあるのだろうか、ちょっと大げさかもしれませんが、そう思うんです。
怒りや悲しみ、悔しい、嫉妬などのネガティブな感情は開運から遠ざかるからと手放しなさいなんて言うけども
私はそれらの感情としっかり向かい合った上で、自分自身や自分と関わってくれる人々へ「感謝して生きる」
これが開運に繋がると思うんです。
映画「国宝」は、善い自分も醜い自分も抱きしめて生きることの尊さを教えてくれる作品でした。
善い自分も、醜い自分も統合して人生を生きるからこそ、人は美しい。
私はそのように感じます。